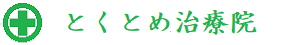1.漢方赤ひげ堂
竹内信幸(竹内信賢)院長をはじめ、既に門を出ていらっしゃる先生方、後を継がれている先生には大変お世話になりました。たった丸二年間の修業期間でしたが、貴重な臨床経験となりました。
赤ひげ堂に入門すると、その志を試すかのように容赦ない洗礼を浴びることとなりました。今の時代風潮からすると社会問題となるようなことばかりでしたが、それに負けてしまうような生半可な覚悟では何も成し遂げることはできないのだと思います。
この業界で初めに戸惑うことは同じ手技でも教わる先生によって全く違う説明をすることです。A先生から教わったことをB先生にそのままやっても合格を頂くことができないのです。これは各個人で感受性が違う為であって、同じものであっても感じ方に差異が生じるからなのだと思います。
私は赤ひげ堂にいる色んな先輩から指導を受けたため、練習をする時はその都度手を変えて凌いだ記憶があります。また私はどんな先輩方でも練習から逃げることは一切しませんでした。従って練習量は誰にも負けないくらい※<注1>だと思います。それを繰り返していくと教える先生の良し悪しも解かるようになってまいります。しかしどんな場合にしろ、きちんと立場を弁えて相手を尊重する心構えと言動がなければ自身の向上はなく上達もありえません。意外にも自分の苦手とする相手から学ぶことは実に多いのです。初学生で辛抱が出来ずに脱落していく人もいますが、こういったことが本当の修業のように思えます。
このように頑固な私が色々な先生から指導を受けたことによって、ありとあらゆる流派の違いを区別できるようになってきます。そうしたことが相手との共感力が身に付き、百人百色である患者様の訴えが解かるようになってきたのです。そうすると相手に合わせて手技を施せるようになり、今現在はどんな人でも合わせられるようにはなっているとは思いますが、最近は自分の味をありのまま出している気がします。
一方の竹内院長先生はというと第三の眼が開眼しており透視能力を持ち合わせた方でしたが、気性の荒い性格もあり、鍛え甲斐のある弟子に対しては決して手加減することはなく、容赦なく拳で殴ったり物で頭を叩き潰すような師匠です。私も毎日何発も殴られたものです。今の時代だと体罰という批判する声も出てくるかもしれませんが、それでも私は手技の上達をしたいと思いましたので耐えられたのだと思います。病に冒され、深刻な思いで過ごしている患者に対してお粗末な施術を施し※<注2>、金品を受け取ることなどありえない話であって、当院が成果重視を方針に掲げている理由はそこにあります。そんなママゴトのような半端な医療を酷く嫌い、偽りのないものを真剣に探し求めたのです。これは今も変わっていませんが、近頃は随分と楽になって余分な力が抜けています。
そのような青二才である当時の私を見透かした竹内院長は真剣に関わって頂きました。竹内院長は当時の私と同じ年頃には懐に短刀を忍ばせて自刃する覚悟でこの道を歩んでいたようです。そこで編み出した技が「三角相関」と「相似性相関」です。この話を聞いて竹内院長と巡り合ったことになぜか納得しました。
ただ竹内院長と手技練習をする時は具体的指導を受けることは一切ありませんでした。”真の教えは、教えの中にあらず” だからです。これを「教外別伝・不立文字」という禅宗の言葉で言い表されたりします。勿論、練習時にマヌケなことをやると容赦なく拳や蹴りが死角から飛び込んでくることになりますが、そんな竹内院長が私の手技を受けてベタ褒めすることも何度かあったのは覚えています。
私に素質があったのかは分かりませんが、竹内院長が ” 徳ちゃんは自分の信じた道を往きなさい ” と、そのように言われたことが3回くらいあります。普段は鬼のような恐い様相をしている竹内院長が、不気味なくらい静まった機嫌の良い表情なので鮮明に覚えています。私にとって竹内院長の言葉が赤ひげ堂で学び得た一番の財産なのかもしれません。
今現在の私は自分流ではありますが、手の感覚や診断力は赤ひげ堂の道があったからだと感謝しております。また竹内院長が編み出した「三角相関」「相似性相関」は基本理論である経絡経穴論からの派生技として捉え、森羅万象を解き明かす弁証法として拝借しております。この場を借りて感謝の意を申し上げます。
※<注1>
赤ひげ堂では手技練習を行いますが、初めは親指がしゃもじのように膨れ上がります。約1年くらいで親指だけで腕立て伏せができるくらいの指に仕上がります。特に腕立て伏せは出来なくても良いのですが、これがある種のボーダーラインで目安になります。この基礎体力が出来上がると、深い層まで人体が見通せるようになっていきます。これでも半人前にさえ到達しないと私は思います。
※<注2>
赤ひげ堂では国家資格が無いお弟子さんでも、赤ひげ堂に来られる患者様に手技のみを行っています。これは治療家を育てるという方針から来ており、社会的法律上において許されない声もあるかもしれませんが、竹内院長はそれを覚悟の上で全責任を負っています。勿論、主担当の先生は国家資格を有しておりますのでご安心下さい。従って患者様は手技で不満を感じることがあれば遠慮なく主担当の先生に伝えて下さい。主担当が竹内院長の場合も同じくです。その後の惨事は・・・ お察し下さい。。。
2.熊坂武術院
熊坂武術院では故渡辺一先生より受け継がれた熊坂護先生に大変お世話になりました。熊坂先生の関節整復の技は勿論のこと、それよりも関節の原理が感覚的に理解したところに経筋の虚実<注3>や経穴を見出したことが大発見でした。それからというもの揉み技が飛躍的に上達しまして、理学的な運動療法の原理も自ずと整合が取れ、そこに呼吸を加えると一層全身に渡って経筋に気血を巡らせることができました。充分なリハビリテーションとして活用し、関節技を拝借しております。この場を借りて感謝の意を申し上げます。
上記の赤ひげ堂に入門する前から熊坂先生の存在は知っており、本来は熊坂武術院に入門することを考えていました。ところが宇都宮市に在住であった為、新宿区にある鍼灸学校との距離を考えると頻繁に通うことができないと思い先送りすることにしました。
私は教科書から学ぶタイプではなく、先に実践で体を動かして後から教科書を開く学び方でしたので、臨床経験が積めて且つ技術を究めているようなところが上記の赤ひげ堂であった訳であります。結果的に赤ひげ堂の方が “見て触って”の場数や練習量は格段に多く、そのお陰もあって熊坂先生の難解な関節整復法を理解するのが早まったと思います。
鍼灸学校の卒業後も熊坂先生の所へ通いましたので、私が受け持った患者様で改善しなかった場合は熊坂先生の所へ連れて行くこともありました。そこで熊坂先生のやり方を学んだものです。ただ後に私が悔やんだことは、連れて行った患者様から熊坂先生に支払われる施術代を私が立て替えをしなかったことです。患者様からのお咎めは全くありませんでしたが、私の真心の不足さに反省をし、これは早く自分のものにしようと奮い立ったことを覚えています。
熊坂先生の師匠であった故渡辺一先生はあまり技を公開されなかったようで、”自分の代でこの技は終わり” と言われていたお話を伺いました。また効果も凄まじく、周りのお医者さんからよく思われなかったようです。そのようなことが理由なのかは分かりませんが、賽銭箱でやっていたと熊坂先生から聞いたことがあります。
熊坂先生は技を学んでいる時期は、その場で治らなかったりすると夜も眠れなかったと経験談をお話しされたこともあります。私もこの関節技を学ぶにあたり何度も壁にぶち当たりました。師匠の教わった通りやってもうまくいかないのです。そんな時はとても悔しくて、熊坂先生と同じように眠れない日もありました。患者に対して結果で報いることができなかったことがとても苦しかったのです。当時の私は、この時に受け取るお金ほど心痛いものはありませんでした。
こんな素晴らしい技を授かるには、私利私欲に塗れた愚人には到底理解できないようになっているのだと私は思います。たとえ型を学んだとしてもその秘奥にある真髄には達することができず堕落の技に成り代わってしまいます。会津藩に残存した柔術の関節整復法が途絶えなかったのは艱難辛苦に耐え忍んだ熊坂先生のお陰だと思います。
日本古来( 正確には江戸末期だと思います )からある関節整復法を知る方は日本全国を探しても熊坂先生のみで、一応にも私は受け継いでおりますが、この技において「〇〇流」や「誰々を祖とする」といった表現を用いて自らを権威付けすることはいたしません。技や術というものはどれも素晴らしいものではありますが、その極意や根幹にあるのは真理(神理)といったものであります。そして私が関節技を通して辿り着いた境地は ” 往きたいところへ往けばよい ” という苦痛がない楽な道であり、無責任で自分勝手とは違うものでした。
全ての技や術、学問や武芸というのはこのような真理(神理)といった源泉に達する為の方法論にしか過ぎないのだと思います。そしてその源泉は枯れることを知らない無限の力があり、技や術は全てそこから生まれるものであると信じています。つまり自分自身が本物にならなければ、私が受け継いだ技や術も偽りになってしまうということです。まさに 心・技・体 と言ったものでしょうか。日本文化は全て之であり、己の修養にこそ意義があるような気がしています。
<※注3> 経筋の虚実は、経絡の虚実とは異なります。談義の項で述べます。
3.謝辞 ありがとうございました ┌○” ペコリ
正直なところ私がここまで成長できたのは思いもしませんでした。治療家としての腕は立ちましたが、それよりも私が得たものは “命懸け” だと思います。この表現が正しいかどうかは分かりませんが、竹内院長も熊坂先生も施術方法は違えど同じ思いでして、私も真剣に取り組んだものです。きっと多くの先人達も気骨溢れ、心血を注ぎ、自らの人生を終えたのだと思います。
命懸けで行ずれば命の道理というものが明らかになります。この道理を得ずにして戦はおろか、普段口にする食べ物にさえ真の平和を見出すことはできないことでしょう。
人が感動したり喜んでもらったりすることは嬉しい気持ちになり、とてもありがたく私自身が救われるような思いにもなります。今でも先人達が遺していった知恵や技術には敬意を払い、常に拝借する気持ちで施術を行っております。最近ではそのような存在と一緒に施術をしているような感覚で、ご縁のあった方に感応しているような気もいたします。これからも精進を重ね、お役に立てればと思います。
德留 仙要 拝